2019/06/10

広告
PVJapan2015レポート2
- 夏休みの宿題としてたPVJapan2015の詳細レポートの第2弾をお届けします。
いろいろとバタバタしておりお届けが遅くなって申し訳ありません。●PVJapan2015の公式HPはこちら
PVJapan2015 公式HP●私のレポートはこちら
①PVJapan2015に行ってきました&メガ発セミナー2015へ行ってきます!
②最も濃密&勢いのある展示のLooop社|PVJapan2015レポート1 - 第2弾は、太陽光発電システムの花形の太陽光パネル(モジュール)のまとめです。
12社の太陽光パネルが一堂に集結
- 太陽光パネルは国内外の12社が一堂に集まったようです。
もちろん私もすべてのパネルを見て回れたわけではりませんので、PVJJapan会場でいただいた情報誌を見ながらこの記事を書いています。(笑) - さて、太陽光パネルに関する個人的な感想は
「やっぱりよくわからないなぁ」というものでした。というのも、結局パネルって
「モジュール変換効率」であったり、「重量」のような数値と
数値では表せないけども重要な「品質」、このようなもので、ほとんどが決まってしまうと思っています。
ところが、これら目に見えないものを、展示会で見てもぜんぜん面白くない。
- もちろん各社、いろいろなアプローチでこれらの要素をアピールされようとしているのだと思います。
ただし我々一般人からすると、やっぱり同じようなことを聞かされている感じてしまいます。
まぁ、ストレートに言うと
「退屈、退屈、退屈~!」な展示でした。(笑)※そもそもプロ向けの展示会なのでそれでよいのかもしれませんが。
- 今回の展示で太陽光パネルについて感じたことを徒然なるままに書きます。
・そもそもモジュール変換効率の値って公的機関ではかるのでしょうか?
・公的機関で図っていたとしても、その公的機関は各国で、きちんと基準はあわせられているのでしょうか?
・品質なんて、素人やちょっと分かっている気分の人が工場/工程見たってほとんどわからないですよね。
等々。・・・まとまりなくて申し訳ありません。
- ということで、結局、我々素人の一般人がどのようにしてパネルを選ぶかというと、
やっぱり「口コミ」しかないのかなぁとの思いを強くした次第です。
多くの人が、ネットで、
実際に設置した人の発電量はシミュレーション通りか、トラブルは起きていないか調べてみたり、
信頼のおける人に相談したりして、その太陽光パネルが大丈夫かどうか判断をしていると思います。
ほとんどの人にとって、口コミ>基本スペックなのです。
まとめ
- 支離滅裂になってきたので、まとめます。笑
- ○まとめ
・PVJapan2015でも太陽光パネルは展示の花形
・ただし一般人が見ても、数値以外の差はわからない
・実際に太陽光パネルを選ぶときには「口コミ」で選ぼう・・・というところでしょうか。
第2弾からちょっと辛口のレポートとなってしまい申し訳ありません。(^^;




























































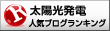
コメント
変換効率については、国際基準で決められています。
同じ照度、角度、距離、時間で測り、光の持つエネルギー=地球に降り注ぐ太陽光のエネルギー(=大気での減損も係数化してます)の何%を電気に変えているかが
変換効率です。
ただ、モジュール効率とセル効率はちがいます。モジュール効率は、パネルのフレームなども含めた面積で発電量を割って効率をだしていますので、これが実効率となります。(日本のJPEAではセル効率表記が多いです)
また変換効率が良いというのは面積あたりでの発電量が多いというだけですので
かならずしも変換効率が良い=発電量が多いとはなりません。
ただ、シリコン結晶型については、原理が同じなので、変換効率=発電量の良さとなります。
パネルを見ても分からないっていうのは、待ってください。
フレームの作りや穴の精度、セルの切り方、セルのバスバーの作りなどに注目してください。
こだわりのパネルはやはり美しいです。安いパネルはやはり、安物とスグ分かってしまいます。
ただ、展示会に出すメーカーはそれなりなんで、ひどいのはないですけどね(w
by 通りすがり(鬼) 2015年9月12日 8:27 AM
>・そもそもモジュール変換効率の値って公的機関ではかるのでしょうか?
https://unit.aist.go.jp/rcpvt/ci/about_pv/output/measure.html
世界標準の測定基準がありますよーーー。
ただ、この測定法は”特定条件での人工光”を使っているため、実際の太陽光下では同じパネル容量であってもパネル種類の違いにより実発電量に差異が出てしまうという問題があります。
一番分かりやすいのがCISのパネルで、CISのパネルは上記の測定法で出力を測定すると低めの数字がでてしまうんですよね。
なので、実際の太陽光ではパネル容量あたりの発電量が他種のパネルよりも大きな値となるという特性となってしまうようです。
おそらく、上記測定法が確立された時点ではシリコン系のパネルしか存在していなかったため、以降開発されたCISに対しては測定基準が対応できていないという状況なのだと考えています。
by 通りすがり 2015年9月12日 8:51 AM
>通りすがり(鬼)さん、通りすがりさん
コメントありがとうございます。
みなさん、お詳しいですね~。私ももっと勉強しないとと反省しました。
>通りすがり(鬼)さん
「フレームの作りや穴の精度、セルの切り方、セルのバスバーの作り」ですね。
今度からその視点で見てみることにします!
>通りすがりさん
なるほど!
「CISのパネルは上記の測定法で出力を測定すると低めの数字がでてしまう」とのこと、CISのパネルがシミュレーション値より発電量がかなり多くなる一因なのかもしれませんね。
by あおそら 2015年9月12日 11:12 AM